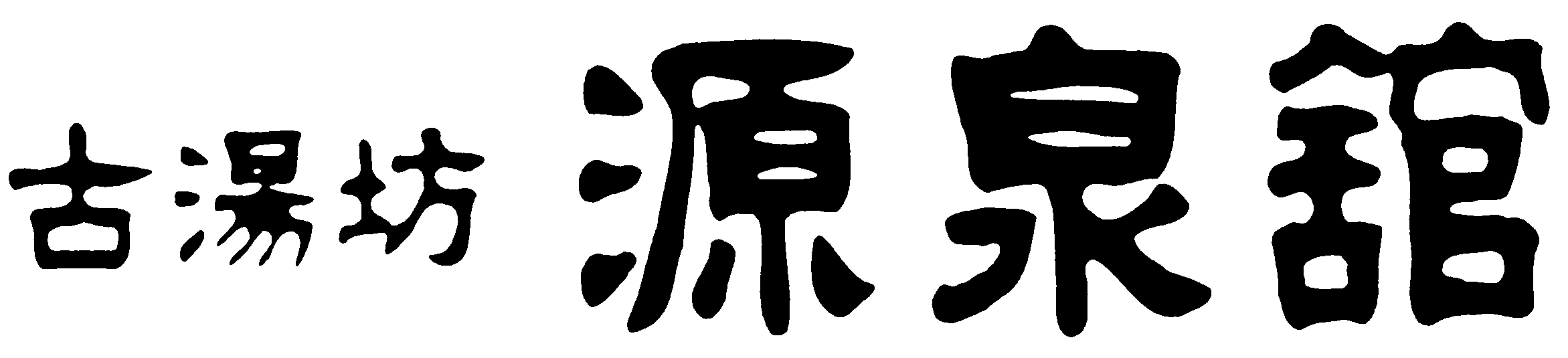“効能”じゃなくて“適応症”?
こんにちは。
今日は、温泉の「はたらき」について少し真面目に。
以前しゃちょーがおたよりにも書いたことある内容です。
よく温泉の紹介で「〇〇に効く!」という言い方を見かけたことがある方、多いと思います。
実は「効能」という言葉、本来は薬に使う専門用語。
温泉でそれを使ってしまうと、薬機法(旧薬事法)に抵触してしまうおそれがあるのです。
では温泉は何に「効く」と言ったらいいの?というと…
正しくは「適応症」といいます。
この「適応症」は、環境省が定めているもので、たとえば「神経痛」「関節リウマチ」「冷え性」「疲労回復」など。
でもこれも、「治す」という意味ではありません。
あくまで「温泉に入ることで、その症状がやわらぐことが期待できますよ」という、やさしい後押しのようなものです。
温泉の力は、「治療」よりも「予防」。
西洋医学のように病気を直接治すというより、体調を整えて、病気になりにくい体づくりを手伝ってくれる――そんな存在です。
だからこそ、日々の暮らしの中に温泉を取り入れて、ストレスを軽くしたり、免疫力を高めたりすることが大切。
特に現代は、ストレスが体調を崩す原因になることも多いですからね。
「最近ちょっと疲れたな」
「病気じゃないけど、なんとなく不調かも」
そんな時こそ、ぬる湯の温泉にじっくり浸かって、心と体をゆるめてみてください。
源泉舘も、みなさんの“予防”の場として、お役に立てたらうれしいです。
といっても火傷とか切り傷とかほんとに良くなっちゃうので、わたしたちも「治った!」って言っちゃうんだけどね笑